泉大津を知る

目次
見たい情報をクリックしてください。その情報にリンクします。
| 市の生い立ち | 位置、市域面積、アクセス |
| 市章、シンボルマーク、イメージカラー、ブランドメッセージ、マスコットキャラクター | 人口(統計) |
| 産業の歴史 | 特徴的な取り組み |

大津の地名は、古くから随筆や紀行の中で、小津の泊、小津の松原、大津の浦などと記され、名勝の地として知られていました。土佐日記の中でも、紀貫之が「行けどなお行きやられぬは妹がうむ小津の浦なる岸の松原」と記しています。
明治22年4月1日、市町村制の施行によりそれまでの17か村が大津村、穴師村、上條村に統合され、和泉郡の所属となりました。その後、大津村は大正4年4月1日に町制を施行して大津町と改称し、昭和6年8月20日に穴師・上條村を合併したのち、昭和17年4月1日に市制を施行(府下7番目)、泉大津市と改称して今日に至っています。
位置・市域面積・アクセス
位置
本市は、大阪府の南部に位置し、北部・東部は高石市と和泉市、南部は大津川を境として泉北郡忠岡町と隣接しています。西北部は大阪湾に面し、はるかに六甲山、淡路島を望むことができます。
地形は市内全域がほぼ平坦で、市内全域が市街化区域になっています。
市域面積
市制施行当時の市域面積は、8.20平方キロメートル、人口は33,307人でした。その後、市勢の発展と、臨海部の埋め立てにより、市域面積は14.33平方キロメートルとなっています。(出典:「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」(国土交通省))
(東西南北端点の緯度経度)
| 東端 | 西端 | 南端 | 北端 | |
| 緯度 | 135° 26’ 06” | 135° 22’ 02” | 135° 24’ 53” | 135° 22’ 44” |
| 経度 | 34° 30’ 33” | 34° 31’ 01” | 34° 28’ 56” | 34° 31’ 59” |
(出典:市区町村の位置情報」(国土交通省))
アクセス

鉄道
市内に3駅、快適にアクセス
南海本線「北助松駅」「松ノ浜」「泉大津」の3つの駅があり、わずか20分で難波、関西国際空港にアクセス。快適で市民の足となっています。
車
大阪市内まで30分
高速道路の出入口が2か所あり、大阪市内へは約30分、和歌山へは約40分。神戸や京都へも1時間前後で行くことができます。
船
長距離フェリーも運行中
泉大津港と北九州・新門司港を結ぶ、長距離フェリーが運航し、紀州への玄関口になっています。

市章
泉大津の「泉」と「大」の文字を波形に図案化し、湧きのぼる発展と海外への雄飛を表象しています。 昭和17年9月25日制定。

シンボルマーク
毛布のまち泉大津にふさわしく羊の顔をイメージし、目と口の黒い丸は「創造」「躍動」「調和」を表しています。

イメージカラー(オヅブルー)
(一般名称:ターコイズブルー・あおみどり) 古くから本市と関わりの深い海と、クスノキ(市の木)や松の木などのみどり。 海の「あお」と植物の「みどり」を重ね合わせた泉大津にぴったりの色 (市民アンケート1位あおと2位のみどりの中間色)
※シアン60、イエロー20

ブランドメッセージ
未来を見通し、新しことにチャレンジしてきた泉大津市には、さまざまな新しいことがあるらしい…。調べて、訪れて、暮らして確かめて欲しいことを訴求しています。

マスコットキャラクター
市制施行70周年を記念して誕生した羊のキャラクター「おづみん」。 「おづみん」の「おづ」は同市域が古くから「小津」と呼ばれていたことから名づけられました。 市のマスコットキャラクターとして、毛布・ニットのまち泉大津を全国にPRします。
産業の歴史
織物産業の伝統
天下に知られた泉州木綿
17世紀ごろから庶民の衣料として広く利用され始めた綿織物。なかでも泉州は、「堺より比の間(樫井)に至る凡そ五、六里ばかり、海に沿ひて平田の間を行くに、極目皆木綿(目に見えるものはみな木綿)」と伊藤東涯による紀州道中紀行に紹介されているとおり、全国有数の綿作地でした。 1785年、宇多大津村に綿花売買の注文所ができ、大津村の人々はしだいに綿の生産から加工や商いへと手を広げていったようです。
さかのぼれば、真田幸村へ
織物の伝統をさらに遡れば、天保の飢饉の際に、人々がこれを織ってしのいだという真田紐。 「真田幸村が考案し、後藤又兵衛が当地に伝えた」という伝承もあり、木綿平織りのかっちりとしたこの紐を織る技術が、後の織物のまちとしての素地を作ったともいえそうです。
マニュファクチュアの先駆者
1842年(天保13年)の記録によると、宇多大津村には、農家ではない10軒を含む18軒の織屋があり、近隣の村からも含めた通勤賃織り日雇い82人など、137人の労働者が働いていたとか。ほかにも住民の大部分が綿賃打、糸稼、染屋などに従事している工業の村であり、すでにはっきりと、資本家と労働者の分業という形態がとられていた様子がみられます。 これは、酒造の灘と並ぶ、我が国で最も早いマニュファクチュア(工場制手工業)の始まり。 泉大津は、織物の先進地であるだけでなく、近代資本主義においてもパイオニアだったのです。

毛布王国
全国シェア約90%その底力
暮らしに産業が溶け込んでいる、日本一の毛布のまち
国内で生産される毛布の約90%が泉大津とその近隣地域で生まれています。まさしく泉大津は、日本一の毛布のまちなのです。 以前は、「○○工場」「□□毛布」などと看板を掲げた工場があちこちに見られました。しかし、工場といっても広さは、大きな屋敷ぐらいのものが多く、民家の並びにごく自然に溶け込んでいました。 この「あるのがあたりまえ」の日常性が、紡績・織り・起毛などの分業によって得た競争力とともに、日本一の毛布産業の発展を支える力になっていたのかも しれません。
丈夫でしなやか、しかもソフトな肌触りのマイヤー毛布
今の毛布の主流は、マイヤー毛布です。 2枚の地布を編みながら、同時に毛足となるパイル糸を編み込み、間をカットして2枚に分離させ、表裏を逆にして、張り合わせて仕上げます。 この「編む」という技術で、しなやかで毛足の長い、ソフトな感触の毛布になります。 染めはシルクの版を何色も重ねる方法で行います。 技術は、着実に進歩しており、ぼかしのはいった繊細な柄もきれいに染まるようになりました。 「特別難しいことはないよ」と、ある染め職人は言いますが、「日本一の毛布のまち」を築き上げたのは、まさに彼ら、泉大津の人たちなのです。
パイオニア精神が今日の隆盛のカギ
明治20年、日本初の毛布が泉大津で誕生しました。 素材は、牛毛。
最初は、服地をつくりましたが、ゴワゴワしているのと、においのために売れずに寝具に。「赤ゲット」と呼ばれ、庶民の憧れの的だった舶来毛布には遠く及ばない代物でした。 しかし人々は、柔らかな肌触りを求めて悪戦苦闘し、乾燥させたアザミの実であるチーゼルによる起毛など、さまざまな技術を生むことになったのです。 このときの毛布との格闘が、大きな力となり自信となったのは間違いありません。 大正時代、不動の地位を得た後も、プリント技術などで常に一歩先を行くパイオニア精神は、今も健在です。

ブランケット

工程

ニットマシン
ニット産業
新しい主翼―ニット産業
今後の発展が楽しみなニューパワー
大阪という大ファッション市場に近い地の利を生かし、戦後、急速に伸びたのがニット産業です。 急速な流行の変化や高級化・個性化といった消費者のニーズに応えられる国内有数のニット(横編み・丸編み)産地として、アパレル業界からも高い信頼を得ています。 その背景には、高度な機能を持った編み機や色・柄をコンピュータでデザインするシステムなど、最先端技術を追及するといった努力がありました。 今後は、高付加価値時代に売れる商品づくりを目指します。

こころとからだの健康、産地の未来
CO-ON(コ・オン)
CO-ONは、泉大津市立図書館シープラ内に「こころとからだの健康、産地の未来」掲げるコンセプトショップです。
店舗では、リビングケットなどの寝装具や、ベビースリーパーやセーターなどの衣服、手芸用毛糸といった雑貨に至るまで、多岐にわたる泉大津産の繊維製品を揃えています。商品は、手に取ることができ、購入することも出来ます。
ぜひ、お越しください。
あしゆびプロジェクト
幼児期から、あしのゆびを使った良い姿勢を覚え、日常の遊びや生活の中であしゆびを鍛えることは、体幹を安定させ、生涯寝たきりにならずに健康な体を維持するための土台づくりにつながると考えています。
マタニティ応援プロジェクト
市では、令和5年4月から妊娠している人の健康づくりを応援するため、東洋ライス株式会社と連携し、多くの栄養素を含んだ「金芽米(きんめまい)」を妊娠している人に毎月最大10キログラムをプレゼントしています。

オーガニック食材を取り入れた給食
保育所や認定こども園、小中学校で提供する給食で様々な取組みを実施しています。オーガニック食材や農薬の使用量を減らしたお米を栄養価が高くおいしい「金芽米」に加工して提供するなどこどもの健全な身体づくりを推進しています。

多様な教育の場の充実
イベントを年間400回実施している図書館「シープラ」やまち全体を舞台に「文化・芸術」を気軽に楽しむことができるイベント「まちなかアートフェス」、子どもの金銭感覚を養うことができる体験型イベント「キッズフリマ」など学校の枠を超えた多様な教育の場があります。

子どもの居場所づくりと家庭教育支援
学童保育の待機児童を出さない取組みや延長預かり、子どもの居場所づくりのための放課後子ども教室、家庭での学習習慣を身に着けっるための学びっこ支援ルーム、保護者を支援するための訪問型の家庭教育支援などを実施しています。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




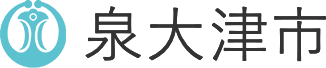





更新日:2025年11月14日