受動喫煙の防止について
受動喫煙とは
喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
受動喫煙 – 他人の喫煙の影響
たばこの煙は、喫煙者の口を通して吸い込まれるものを主流煙と呼び、先端の点火部分から立ち上る煙を副流煙と呼びます。副流煙に含まれる化学物質は、主流煙に含まれる成分とほぼ同じですが、主流煙よりも多くの有害化学物質を含むことがわかっています。喫煙者が紙巻たばこ1本を吸った際には、その30~40%が主流煙となるのに対し、50~60%は副流煙の発生源となります。また、一般的に副流煙は発生直後から環境中の空気で希釈されるため、主流煙をすべて吸い込む喫煙者と受動喫煙者を比べると、受動喫煙者のほうが有害性が低くなると考えられます。しかし、空間の狭い車両中などでは副流煙の曝露量が多くなるなど、受動喫煙の健康影響は環境によって大きく変化します。
受動喫煙の科学的な研究は、日本の平山雄博士による報告が世界的に知られています。1981年英国医学雑誌に掲載された、重度喫煙者の妻(非喫煙者)の肺がん死亡リスクについての論文では、本人が吸わなくてもヘビースモーカーの夫をもった女性では、肺がん死亡のリスクが約2倍になると報告されています。以後多くの研究がなされ、さらに複数の研究結果をまとめて推計するメタアナリシス(メタ分析)も行われています。その結果、現在では受動喫煙による肺がんのリスクは1.28倍(28%の上昇)、虚血性心疾患のリスクは1.3倍(30%の上昇)、脳卒中のリスクは1.24倍(24%の上昇)とされています。さらに受動喫煙は子供の呼吸器疾患や中耳炎、乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指摘されています。また、妊婦やその周囲の人の喫煙によって低体重児や早産のリスクが上昇します。
【参考 e‐ヘルスネット(厚生労働省)】
望まない受動喫煙の防止を図るため受動喫煙防止対策
平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。大阪府でも令和元年7月から「大阪府受動喫煙防止条例」による全国トップクラスの対策を実施しています。
改正健康増進法の概要
改正健康増進法は、全面施行されています。平成31年1月24日一部施行され、喫煙者に対して「喫煙をする際の配慮義務、多数の者が利用する施設の管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務」が課せられました。
喫煙をする際の配慮義務
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
・子どもや病気の人など特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所(学校や病院など)では、特に喫煙を控えること
喫煙場所を設置する際の配慮義務
施設管理者は、喫煙場所を設置する際、
・出入り口付近や利用者が多く集まる場所には設置しないこと
・たばこの煙の排出先について周囲の通行量や周囲の状況に十分配慮すること
大阪府受動喫煙防止条例の概要
大阪府では、府民の健康を守るため、2018年7月の「健康増進法」の改正を受け、法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。
大阪府独自の取組
大阪府条例では、健康増進法における受動喫煙防止対策よりも一歩踏み込んだ対策として、2020年4月以降は学校や保健所、病院といった子どもや患者、妊婦などが主に利用する施設および市町村(行政)の庁舎などの敷地内を「全面禁煙」に努めることとし、「特定屋外喫煙場所を設置しないこと」としています。また、これまで段階的に施行をしてきた府条例は令和7年4月1日に全面施行となり、これまで飲食をしながら喫煙ができた飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となりました。
(関連リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
〒595-0013 泉大津市宮町2番25号 健康づくり課(保健センター)
電話番号:0725-33-8181 ファクス:0725-33-4543
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




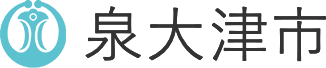

更新日:2025年06月09日